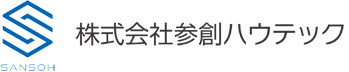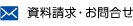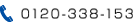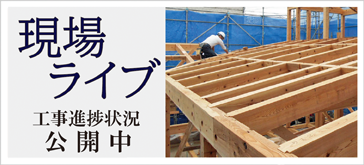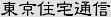社長の寄稿実績
COMPANY
被災地に寄り添うということ

既に震災から4ヶ月余りが過ぎようとしている。いまだにテレビもラジオも新聞も週刊誌も被災地の状況を争うように伝えている。
少し離れた東京にいても「がんばれ」「ひとつになろう」「負けるな」などという企業メッセージが街中に踊っている。一方被災地では、一瞬で「暮らし」と言う名の袋の底が抜けてしまい、今もなお先が見えない生活を余儀なくされている。
こんな状況になると必ずと言ってよいほど「神は人に乗り越えられない試練は与えない。だから頑張って」と誰かが言う。しかし、家も家族も仕事も失った人の前では、こんな言葉は無力だろう。仮に私たちに「はい、がんばります」と答えてもらったところで、表面的な言葉とは裏腹に現実との溝は埋まることはない。
ただただ、途轍もなく長い時間にしがみつきながら、今日より明日、明日より明後日をと、日々を積み上げていくことしかできないのではないだろうか。
震災後、多くの芸人やスポーツ選手、さらに歌手の方々が被災地を慰問に訪れているという。避難所でネタを披露し、子供たちとスポーツを楽しみ、さらに歌を披露し、義援金を集めるなど、その活動は日増しに活発になっているようだ。「私たちにできるのはこれだけ」と、わずかな時間でも被災地と寄り添うことを選んだボランティア活動の輪には感動を覚える。

〔横倒しになったコンクリート造の建築物〕
私自身は、3・11以降は東京にいても震災がらみの様々な対応に追われて過ごした。いや、忙しさを理由に、現実から目を背けていただけかもしれない。私は、神戸にしても、中越にしても、大きな震災がある度に現地に足を運んできた。しかし今回は違った。未曾有の自然災害と相次ぐ余震、さらに追い討ちをかけた原発事故、首都圏も被災地と言わんばかりの風評や都市機能の脆弱さゆえのインフラ不安に巻き込まれ、うろたえていたのかもしれない。
しかし、家づくりに携わる者として、被災地の状況を目の当たりにすることは、今後の住宅建築の実務に役立つはずだ。工務店経営者として、できる限り多くの社員と被災地に行き、被災地を視察しなければという思いが、時間の経過とともに湧き上がってきた。
そして6月上旬、ようやくスケジュールが固まり、当社の現場監督7人と共に被災地に向かった。

〔運ばれる電車の残骸〕
津波被害が大きかった宮城県女川へ向い、石巻市内を流れる旧北上川を渡ると、地盤沈下や切り立った崖が崩れている様子や、津波で流され電柱やブロック塀に乗り上げ、放置されている車両の数々を目にした。また、地盤沈下のため、満潮時になると道路の一部は冠水し、通行止めになるほどだった。
車を進め、内海のため津波被害をあまり受けなかった万石浦を過ぎ、緩やかな坂道を越えたあたりで景色が一変した。海から数十メートルの高さはあろうかと思える場所に建っていたはずの木造の住宅が、基礎と土台を残したまま、架構ごと無くなっていた。また、1階を津波が通り抜けた家の中には、瓦礫や流された車がそのまま入り込んでいた。
さらに車を進めると、言葉を失う壮絶な光景が目に飛び込んできた。津波の凄まじい威力で、鉄筋コンクリートや鉄骨などの堅牢な建物が、瓦礫の中、様々な方向へ倒れていた。澄み切った青い空とコバルトブルーの海にまったく似合わない光景がそこにはあった。
私たちは邪魔にならない場所に車を停め、ヘルメットを被り、建物に近寄って詳細を観察したが、支持杭ごと引き抜かれて倒れた建物、まるで小枝のように簡単に引き千切られた鉄筋、さらには地盤が下がり、足元が水没する建物など、見る限り設計ミスや施工不良があったわけでもない、人が長い歳月を経て築き上げた建築を、まるで嘲笑うかのように、自然の猛威の爪跡だけが残っていた。
気がつくと、私と数人は車を停めた場所から離れた所まで来ていたが、残りの社員は車の周辺をうろついている様子が瓦礫の向こうに見えた。「せっかく視察に来たのだから・・・」と問うたが、想像を超えた被災地の惨状と、ここで命を失った被災者のことを考えると、カメラを向ける気持ちになれなかった、と異口同音に答えが返ってきた。「私も神戸の時は盗み撮りしているような気持ちになったので、皆の気持ちも分かるが、この悲劇を二度と繰り返さないために今ここにいることを考えてほしい」とだけ伝えたが、少し頷いただけで、それ以上言葉は続かなかった。

〔瓦礫が散乱する女川〕
今しがた通って来た坂道を戻りかけたあたりにある一軒のコンビニが通常どおり営業していた。そのわずか数十メートル手前の場所が津波で生死を分けた分水嶺になったと地元の人は話してくれた。
夕方だったので近くにある高校の下校時間と重なり、コンビニにたむろする茶髪の生徒や友人同士で帰宅する生徒たちと遭遇した。
普段と変わらない高校生がいる。そこにはいつもと変わらない日常がある。しかし、一歩手前に起こってしまった非日常の世界。私たちはそのどちらをも肯定しなければならない。今現実に起こっていることなのだから。
宿泊先の旅館に当社の役員と親交のある仙台在住の建築家・小山公一さんが訪ねてこられた。現在小山さんは、被災地に残った家屋の被災状況の判定の仕事で福島・宮城をかけまわり、八面六臂の活躍をしている。小山さんが持参してきてくれた地元の日本酒で一献傾けながら3・11から今この瞬間までのことをお聞きした。
「私は建築に携わる人間として、できることから、ひとつずつやるだけです」
できることからする。
このあたり前のことが、今被災地で最も求められている、それが被災地と寄り添うということだ、と小山さんは言った。
その一方で、復興プランを机上だけで語り始めた「学識経験者」や政局を睨みながら復興支援の御旗を振る政治家が目立つ。
私たちが直面している未曾有の事態の中で最も問われているのは、心と心が寄り添うこと、そしてその底流にある人間力だと思う。
清水 康弘
新建ハウジング・プラスワン「被災地に寄り添うということ」 2011年7月号 新建新聞社